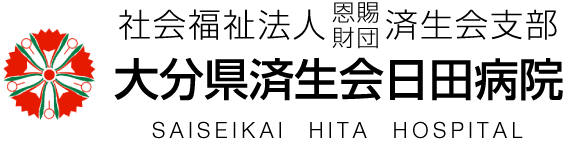脳神経外科
スタッフ紹介
中島 慎治
部長

- 日本脳神経外科学会 脳神経外科専門医
- バクロフェン髄注療法施行認定医
- ゼオマイン施注認定医
- 日本脳神経外科学会 日本脊髄外科学会
- 日本脳腫瘍学会
- 日本頭痛学会
- リビング・ウィル受容協力医師
- 日本定位機能神経外科学会
- 臨床研修指導医 講習会修了
非常勤医師
| 第3水曜日 | てんかん専門外来 吉富 宗健 |
|---|
診療内容
診療対象とする主な疾患
頭痛(特に片頭痛)の診断治療
脳梗塞、脳内出血、脳腫瘍、水頭症および頭部外傷など脳神経外科領域一般の診断および急性期の治療を行っています。さらに治療方針に関するセカンドオピニオンにも対応しています。
特色
- 1.頭痛、特に片頭痛に対する抗CGRP抗体薬による治療
- 2.高品位MRI装置などの各種画像診断装置が豊富です。認知症の診断に有用とされるMRIでのVSRAD解析も行うことが可能です。画像読影に関しても放射線科医とのダブルチェック方式を採用し、より正確な診断を行えます。
- 3.脳卒中急性期治療を終了後は、当院回復期リハビリテーション病棟、あるいは、近隣のリハビリテーション病院と緊密な連携を保ち、早期の在宅復帰を目指します。
- 4.脳疾患後遺症としての攣縮(筋肉がこわばって動かしづらい、痛いなど)に対して、局所へのボツリヌス療法やバクロフェン髄注療法が施行可能です。その他、慢性疼痛に対する脊髄刺激療法なども施行可能です。
頭痛の診療について
頭痛には大きくは一次性頭痛と二次性頭痛があります。
一次性頭痛とは、頭痛そのものが疾患であるもので、緊張型頭痛、片頭痛、群発頭痛などが代表的な疾患です。
二次性頭痛とは、脳腫瘍や脳出血などの疾患の症状として起きる頭痛を指します。
当科では、まず問診、診察の後に高精度の画像検査によって二次性頭痛の否定を行います。その後、一次性頭痛について「どのタイプの頭痛なのか」をしっかりと判断し、頭痛に応じた適切な治療を検討します。
特に片頭痛に対しては、オーソドックスな頭痛薬だけでなく、CGRP関連抗体薬などの比較的新しい製剤から漢方薬まで、様々な薬剤を患者さんの状態に合わせて投薬することが可能です。

- 頭痛は予防、治療をする時代です。
- 頭痛にはたくさん種類があり、何という頭痛かで治療が異なります。
- 市販の頭痛薬や病院で処方される「複合鎮痛薬」は、広く様々な頭痛に効くように、複数の鎮痛成分や精神安定成分などを混合しています。原因となる頭痛の改善に必要でない成分まで含まれる鎮痛薬は、依存や腎障害などを起こすことがあります。
- 適切な診断を受け、頭痛が起きないように予防しましょう。どうしても痛みがあるときには、あなたの頭痛に合わせた適切な鎮痛薬を使用しましょう。
認知機能低下(もの忘れ)について
物忘れは、いずれの年齢層においても多かれ少なかれ見られる症候であり、物忘れがあるからと言って必ずしも病気と言う訳ではありません。また、それは年齢を重ねると頻度が増す傾向にります。
物忘れを来す疾患には様々なものがありますが、その中には投薬治療が可能なものや手術によって症状の改善が期待できるものがあります。物忘れが気になる方はお気軽にご相談ください。
認知症新薬レカネマブ(レケンビ®)について
- レカネマブは「アルツハイマー病による軽度認知機能障害および軽度認知症の進行抑制」の効能・効果のある注射薬です。
- 当院では「初回投与施設」において6か月以上投与した患者さんに「フォローアップ施設」として投与が可能です。
- 医師数の基準を充たさないため当院での初回投与はできません。
- 初回投与を希望される方は投与適応検討の上、初回投与可能施設にご紹介することが可能です。
神経痛・痙縮(けいしゅく)外来について
慢性的な神経痛・筋肉のこわばりでお困りの方はいませんか?
症状にお困りの方はお気軽にご相談ください。